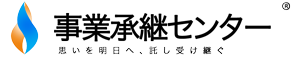不動産については、その売買と運用の問題がありますが、それぞれ極めて複雑な問題を含んでいます。売買時には、売買契約の成立が有効であったか、取得後、契約不適合(瑕疵)が発見された場合には、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の問題となります。運用とは賃貸借ということになりますが、土地と建物では法律の枠組みが違い、また、いつ始まったかによって適用法規が異なってきます。
①不動産・賃貸借その1:売買契約の成立
②不動産・賃貸借その2:契約不適合責任(瑕疵担保責任)
③不動産・賃貸借その3:使用貸借
④不動産・賃貸借その4:土地の賃貸借
⑤不動産・賃貸借その5:建物の賃貸借
⑥不動産・賃貸借その6:賃料不払いの場合
⑦不動産・賃貸借その7:用法違反の場合
⑧不動産・賃貸借その8:立ち退きにあった場合
①不動産・賃貸借その1:売買契約の成立
土地や建物の売買契約となると、高額の取引になりますので、売り手、買い手とも慎重に行動しているはずです。しかし、それでも問題が起こる場合があります。しばらく前に地面師に積水ハウスが55億円をだまし取られるという事件がありましたが、こうした詐欺の対象となる取引もあります。また、売り手が相続をしたばかりで路線価評価で売ってしまったが、時価が路線価の3倍もすることを知らなかったという場合に錯誤を主張してくるというケースもあります。
②不動産・賃貸借その2:契約不適合責任(瑕疵担保責任)
売買契約が成立し、土地や建物の引渡も終わったのですが、土地に建物を建てようとして掘り返したらコンクリートガラがザクザクと出てきた、土に油が混じっているので調査したら土壌汚染があった、建物に住み始めたらめまいがするようになったので、調べてみると床が傾いていた等々、後になって契約不適合(瑕疵)を発見する場合があります。こうした場合には、買い手は売り手に対して、責任を追及していくことになります。責任追及の方法としては、履行の追完請求、代金減額請求、損賠賠償請求、解除等を行っていくことになります。責任追及の期間は、契約不適合を知ったときから、1年以内に通知をしないといけないと定められています。ただし、以上の適用があるのは、2020年4月1日以降の売買契約についてであり、それ以前の契約については、改正前の瑕疵担保責任の規定が適用されますので、要注意です。
③不動産・賃貸借その3:使用貸借
土地や建物を使用する場合、お金をちゃんと支払って借りるのが賃貸借、ただで借りるのが使用貸借です。親子間で親が持っている土地の上に子が自宅を立て、お金を支払わずに使っているという場合が使用貸借に当たります。子が固定資産税を支払っても、無償で使っているとみなされ、賃貸借とはなりません。使用貸借は、期限が決まっていればその期限に、目的に従った使用収益が終了した時、使用収益に足りる期間を経過時、借主の死亡時等に終了します。このように無償の契約でありながらも、一定期間の使用収益が認められているので、貸した側が無償だからいつでも返してもらえるに違いないという期待を持っているとするとトラブルになります。例えば、先の例で子が死亡し、親が子の配偶者と仲がわるかった場合などは、親が出ていけということもあり得ます。これでは、子の配偶者が路頭に迷ってしまうことになりますので、子の相続人が使用貸借を引き継ぐというように解釈されます。使用貸借は対価の支払いを伴わない無償の契約ですが、貸している方と借りている方との期待が食い違うことも多く、トラブルになりがちな契約形態と言えます。
④不動産・賃貸借その4:土地の賃貸借
一言に土地の賃貸借といっても、どういう場合かによって、法律の規定は異なっています。土地賃貸借について何らかのトラブルになった時は、まず、以下のどれに当たるかをハッキリさせてください。
ア 建物所有目的の土地賃貸借
A 旧法借地権
1992年8月より前から土地を借りている場合は「借地法」(旧法)が適用されます。契約期限は決まっていても、更新することにより半永久的に借りることができます。 木造などの場合、存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年となっています。鉄骨造・鉄筋コンクリート等の堅固建物は60年(最低30年)、更新後の期間は30年となっています。現在でも多くの借地に適用があるので、現行借地借家法との内容の違いをよく理解しておくことが大切です。
B 現行の借地借家法の適用を受ける借地権
1992年8月以降から借り始めた場合は、現行の「借地借家法」が適用されます。借地借家法には5つの種類があり、普通借地権と定期借地権が存在します。
a. 普通借地権
契約期限は決まっていますが、更新することにより半永久的に借りることが可能です。 存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となります。
b. 定期借地権 (一般定期借地権)
住宅用として土地を賃借する場合の契約です。契約期間は50年以上とされますが、更新はなく契約終了後は更地にして返還することになっています。定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンション等が、最近では売り出されていますが、期間の終了時に更地にして返さなければならない点は、高い費用がかかるので要注意です。
c.事業用定期借地権
事業用(店舗や商業施設等)で土地を借りる場合に利用されます。契約期間は10年以上50年未満(2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下でした)。これも、契約終了後は更地にして返還することになっています。
d.建物譲渡特約付借地権
契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取ることになります。 契約期間は、30年以上です。
e.一時使用目的の借地権
工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる場合に使われます。
C 建物所有目的以外の土地賃貸借
駐車場、資材置き場、太陽光発電施設、大型プラント、ゴルフ場やスキー場といった、建物の所有を前提としない土地利用の場合は、民法のみが適用されます。一部の用途では建物が建てられることがありますが、施設の管理棟や配電設備などの暴風雨を目的とした建物は借地借家法の適用とはなりません。この場合には、民法の賃貸借の規定が適用され、存続期間の上限が20年から50年に延長されることになりました。
⑤不動産・賃貸借その5:建物の賃貸借
建物の賃貸借契約に、普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があります。
A 普通建物賃貸借契約
居住用・事業用いずれも可能で、賃借の期間については制限がありません。1年未満の場合、期間の定めがない建物賃貸借契約とみなされます。契約は、口頭でも成立し、契約の更新が可能です。家主側は、正当事由がない限り更新拒絶ができません。この正当事由がクセモノで、家主側は自分がその建物を使用する理由等を主張することになっているのですが、実際上は立ち退き料の積み上げを要求されます。賃貸アパートの立ち退き等の場合には、6か月~12か月の家賃が要求されることが多いようです。
B 定期建物賃貸借契約
期間の定めのある建物賃貸借契約のうち、賃貸借契約の更新が認められず、 契約期間の満了により、確定的に賃貸借が終了する賃貸借契約をいいます。公正証書若しくは書面で契約する必要があります。また、賃貸人が賃借人に対して、「契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了すること」を、 その旨が記載された書面により説明することも必要です。仮に説明がなされなかった場合には通常の建物賃貸借となります。
最近オフィスビルの賃貸では、この定期建物賃貸借契約が広く採用されるようになっています。オフィスを借りておられる会社は、一度、賃貸借契約が普通か定期かをよく確認しておく必要があります。
⑥不動産・賃貸借その6:賃料不払いの場合
賃料の不払いの場合には、まずは賃貸人から賃借人に対して、賃料を支払うように請求します。それでも支払ってこないということになれば、弁護士に頼んで内容証明郵便を送ってもらいます。何か月にもわたって支払ってこない場合には、信頼関係が破壊されたと言って、賃貸借契約を解除することが可能となります。そして、立ち退き訴訟も提起できるようになります。
⑦不動産・賃貸借その7:用法違反の場合
賃借人が勝手に第三者に転貸してしまったというような場合には、まずは賃貸人から賃借人に対して、転貸をやめるように請求します。それでも、転貸をやめないということになれば、弁護士に頼んで内容証明郵便を送ってもらいます。どうしても転貸をやめない場合には、信頼関係が破壊されたと言って、賃貸借契約を解除することが可能となります。そして、立ち退き訴訟も提起できるようになります。
⑧不動産・賃貸借その8:立ち退きにあった場合
都会では再開発案件も多く、地上げした業者が、ビルのテナントに対して立ち退いてほしいと申し入れてくることがあります。これは建物賃貸借契約の中途解約にあたりますので、賃貸人に正当事由が具備されているかが焦点となります。賃貸人も、再開発が正当事由となるとは考えておらず、立退料を積んできます。後は、賃貸人と賃借人の交渉になります。賃貸人は一刻も早く出てほしい、賃借人はできるだけ高い立退料を得たいということで、中々合意に至りません。賃貸人の側では、10件いるテナントのうち9件の立ち退きに成功しても、残りの1件が出てくれない限り、再開発に着手できないので焦ります。こうした交渉は、当事者間でも可能ですが、双方とも弁護士に依頼して、適正な立退料のレベルでの和解を図る場合がよく見受けられます。