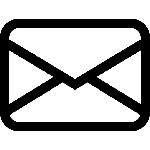公開日: 更新日:
下請の施工ミスが生じた場合における元請と下請の責任分担
下請の施工ミスがあった場合、元請けはどこまで責任を負うのでしょうか。
端的に答えれば、施主との関係では、元請けがすべての責任を負うことになりますが、元請けと下請けとの責任割合は、そのミスに対する寄与度によることになります。
目次
Ⅰ まずは、施主への対応が重要
発注者である施主は、どこまでの施工が元請けによって行われ、どこからが下請けによって行われたかを知りません。あくまで、施主の契約の相手方は元請けのため、施主が引き渡しを受けた物件に欠陥や不具合がある場合、施主からの問い合わせやクレームは、元請け宛てに来ることがほとんどです。
施主との関係では、元請けが全責任を負いますので、問い合わせやクレームを受けた場合には、工事を施工した下請けの問題ではなく、元請け自身の問題として適切な対応を取ることが必須です。
そのためには、現場の状況を確認し、写真を撮るなどして記録に残し、その部分を施工した下請けと補修、代金の減額、損害賠償等についての話し合いを行い、それを踏まえて施主に対して、具体的な提案を行うようにすることが必要です。
ここでは、施主から元請けが追及される責任の内容を見ておきましょう。令和2年4月1日の民法の改正により、その前後で適用される責任の内容が変わっています。
(1)契約不適合責任
施主との請負契約が令和2年4月1日以降に締結されたものである場合には、改正後の民法が適用され、元請けは契約不適合責任(民法559、636、637条)を追及されます。
契約不適合とは、元請けが施主に引き渡した物件が「契約の内容に適合しない」ことをいい、たとえば、契約で合意した性能や仕様を満たさない場合などが該当します。
契約不適合が認められれば、施主は、元請けに対し、① 修補請求、② 損害賠償請求、③ 代金減額請求、④ 契約の解除を行うことができます。契約不適合責任の時効期間は、物件の引き渡しから10年、施主が契約不適合を発見してから5年です。
しかし、この期間内であっても、契約不適合を発見してから1年以内にその旨を元請けに通知しなければ、施主は権利を行使することができなくなります。
(2)瑕疵(かし)担保責任
施主との請負契約が令和2年3月31日以前に締結されたものである場合には、改正前の旧民法が適用され、契約不適合責任ではなく瑕疵担保責任(改正前民法634~640条)を追及されることになります。
瑕疵とは、物件が通常備えるべき性能を欠いていることをいいますが、契約不適合と同じ意味であると考えておいて問題ありません。瑕疵担保責任では、①修補請求、② 損害賠償請求、③ 契約の解除が可能で、契約不適合責任よりも施主の行使できる権利の範囲が、代金減額請求がない分だけ、狭くなっていました。しかも、契約の解除は、建物の建築工事に関しては行うことができないとされていました。
引き渡しから10年で時効にかかり消滅する点は契約不適合責任と同じでしたが、瑕疵を発見してから1年以内に権利を行使しなければならないとされており、通知すれば足りるとされている契約不適合責任と比べて、施主の負担が大きい定めとなっていました。
Ⅱ 下請会社への初動対応
施主との対応は元請けが行うこととなりますが、下請けの施工ミスがあれば、下請けに対して責任を問うことが可能です。
元請けと下請けのどちらがどれだけ責任を負うのかは、元請けと下請けとの間の請負契約でどのような定めがあるかによって決まります。
契約書で責任割合を定めていれば、基本的には契約書の定めのとおり責任割合が決まりますが、契約書に何の定めがなければ、ミスの内容、元請け・下請けの過失のミスに対する寄与度等をもとに責任割合を考えていくということになります。
元請けとしては、まずは契約書の条項をよく読んで、損害の分担についての定めがあるかを確認し、取り決めがあればそれに従います。なければ、元請けと下請けの担当者の話を聞いて、ミスに対する寄与度を確定していくことになります。
Ⅲ 下請会社ともめた場合の責任追及
話し合いで解決すればいいのですが、協議が調わないときには、法的手続きを検討することになります。
建設業の場合、工事請負契約で建設工事紛争審査会でのあっせん、調停、仲裁を紛争の解決方法として指定している場合があります。あっせん、調停の場合には、双方が合意しないと和解が成立しませんので、合意が成立しない場合には、裁判所に訴えを提起することになります。仲裁の場合には、双方から契約締結時に仲裁合意書が提出され、仲裁の判断が最終判断となることに合意されているので、仲裁が最終的な判断となり、裁判所で争うことはできません。
Ⅳ 元請けと下請けの過失割合に関する裁判例
元請けと下請けがどのような割合で責任を負うかは、個別の事案によって異なるのですが、参考となりそうな裁判例を紹介しておきます。ただし、裁判例は、特殊な事実関係の下での判断ですので、以下がそのまま別の事例に当てはまるものではありません。
ア 東京地方裁判所平成28年10月21日判決
下請けが工事完成前に施工を放棄したため、元請けの負担で工事を続行することを余儀なくされた事案で、元請けと下請けの過失割合が30:70とされた。
イ 東京地方裁判所平成25年5月9日判決
元請けが、外壁工事を下請けに行わせたところ、下請けが建物の基本的な安全性を損なう手抜き工事をした事案で、元請けと下請けの過失割合が25:75とされた。
Ⅴ 下請けのミスによるトラブルが起こったら、早めに弁護士へ相談を
施工ミスによるトラブルが発生した場合、まず、施主との解決を図り、同時に下請けと修補の方法、その費用の負担割合等についての話し合いをしなければなりません。建設工事の場合、修補に多額の費用がかかり、損害賠償となれば大きな金額が支払われることになりますので、客観的資料に基づいて厳格に事実を分析した上で、解決策を講じていく必要があります。
建設会社の社員には、慣れない仕事であるため、負担が重く、また、施主、下請と厳しい交渉をしていかなければならないので、精神的な負担も大きくなります。
こうした建築紛争解決に経験のある弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として、依頼者の意向を反映して動いてくれますので、社員の負担軽減につながります。
また、客観的資料に基づいて、当事者にとって公平な解決策を提示してもらえるので、よりスムーズな紛争の処理につながるものと思います。
建設業向けの顧問弁護士サービスについて
青山東京法律事務所の「建設業向けの顧問弁護士サービス」は、建設業特有の法的課題に対処するための専門的なサポートを提供しています。
具体的には、施主・元請との代金未払い問題や工事のやり直し要求、下請業者との契約トラブル、労務問題(偽装請負、長時間労働、労働災害、パワーハラスメント)など、多岐にわたる問題に対応しています。
詳細は、以下ページをご覧ください。
監修者

植田 統 弁護士(第一東京弁護士会)
東京大学法学部卒業、ダートマス大学MBA、成蹊大学法務博士
東京銀行(現三菱UFJ銀行)で融資業務を担当。米国の経営コンサルティング会社のブーズ・アレン・アンド・ハミルトンで経営戦略コンサルタント。
野村アセットマネジメントでは総合企画室にて、投資信託協会で専門委員会委員長を歴任。その後、レクシスネクシス・ジャパン株式会社の日本支社長。
米国の事業再生コンサルティング会社であるアリックスパートナーズでは、ライブドア、JAL等の再生案件を担当。
2010年弁護士登録。南青山M's法律会計事務所を経て、2014年に青山東京法律事務所を開設。2018年、税理士登録。
現在、名古屋商科大学経営大学院(MBA)教授として企業再生論、経営戦略論の講義を行う他、Jトラスト株式会社(東証スタンダード市場)等数社の監査役も務める。